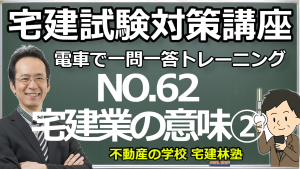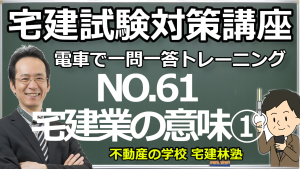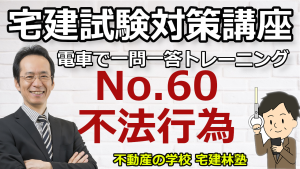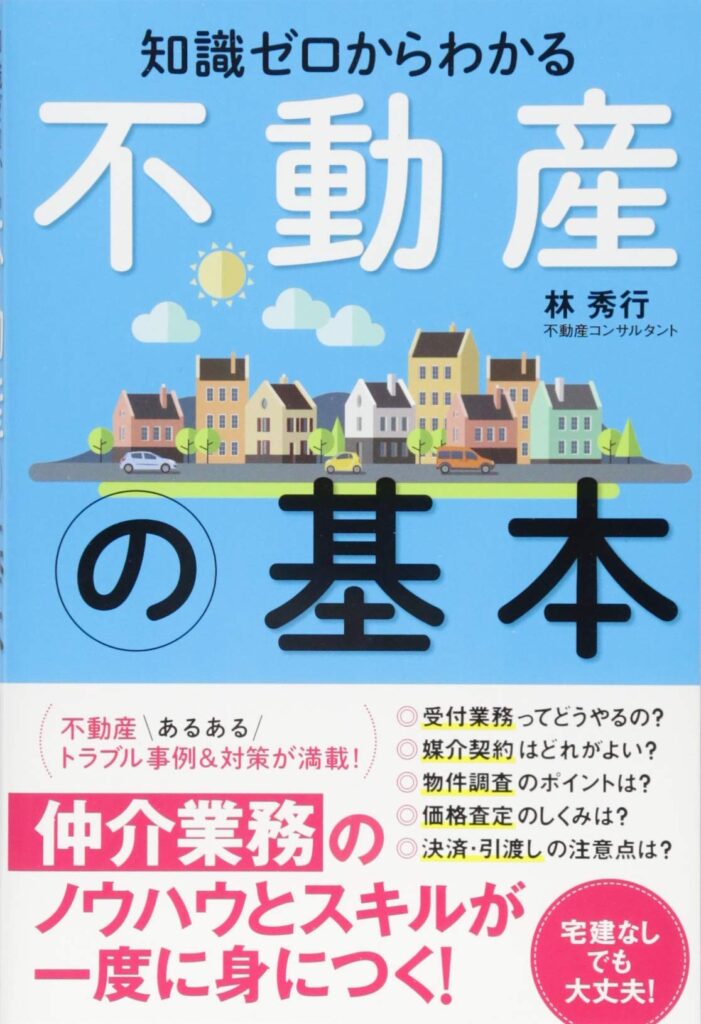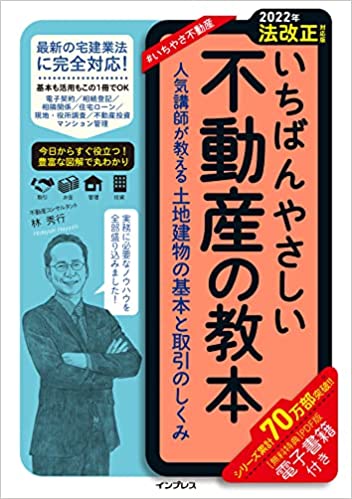【問62】正誤問題
[小問1]
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸借の契約をBの代理により締結するとき、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許が必要である。
[小問2]
Aが、自己所有の土地の上に10戸のマンションを建築し、Bに一括して媒介を依頼して分譲する場合、A及びBは、ともに免許を要する。
[小問1] 解答: 正
解説:
Bは、Aを代理して賃貸を行っているから、宅建業の免許を要する。
また、Bがした契約の効果はAに帰属し、Aは、「自ら貸借」を行っていることになるので、「取引」にあたらず、宅建業の免許を要しない。
[小問2] 解答: 正
解説:
Aは媒介を一括して依頼しているが、結果的に自らマンションの分譲を行っている以上、免許を要する。Bも、マンションの分譲の媒介を行っているから、免許を要する(業法2条2号)。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
解説動画は下の画像をクリック