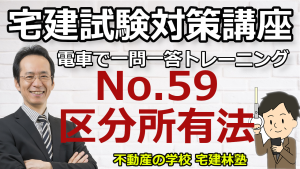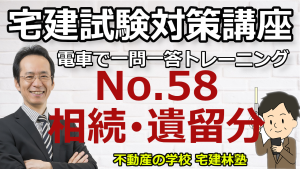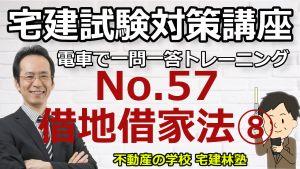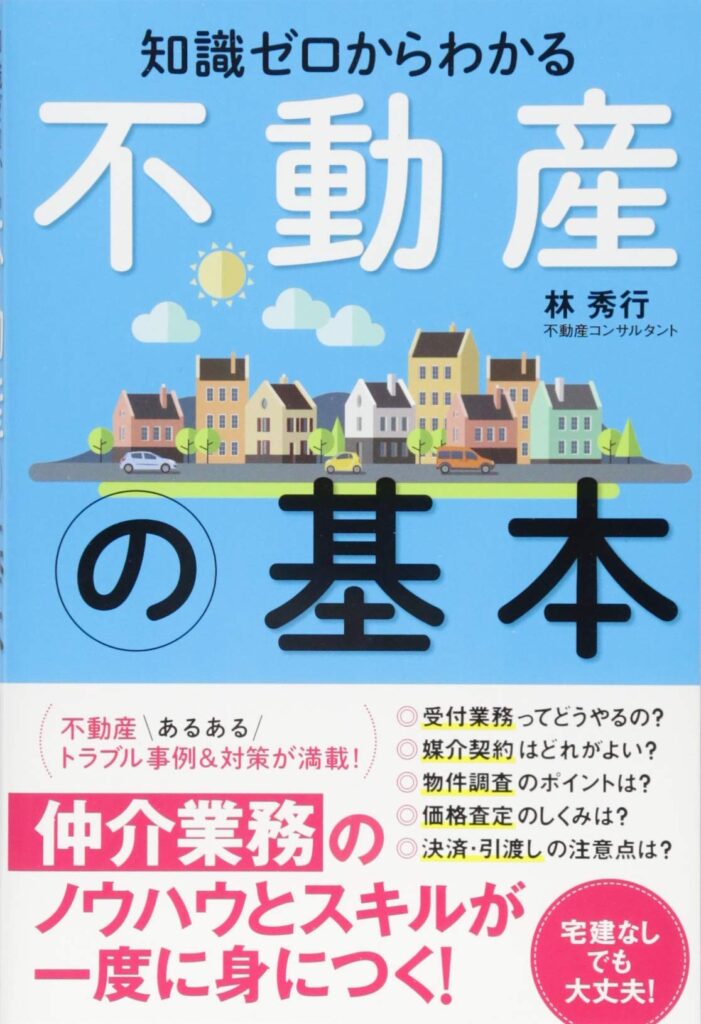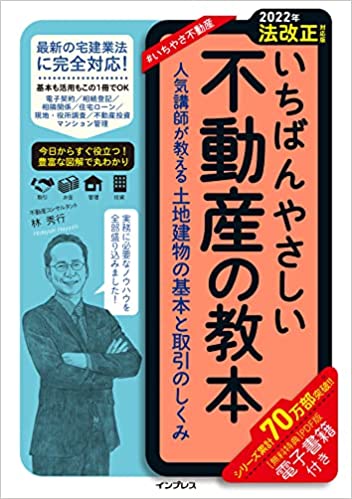【問59】正誤問題
〔小問1〕
建物区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面又は電磁的方法による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができない。
〔小問2〕
建物区分所有法によると、他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書により、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定めを規約で設定することができる。
【解答】 小問1:正
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者が1人でも反対するときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができない。よって、正しい。
【解答】 小問2:誤
「最初に」建物の専有部分の「全部を」所有するものは、「公正証書により」、一定の事項についての規約を設定することができる。
他の区分所有者から区分所有権を譲り受けた者は、「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者ではないから、規約の設定をすることができない。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
解説動画は下の画像をクリック