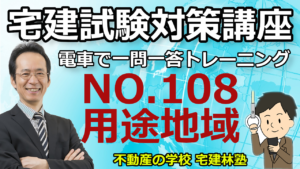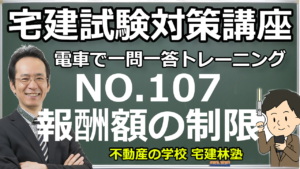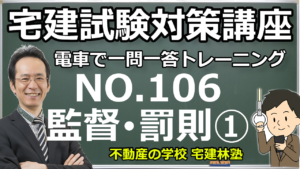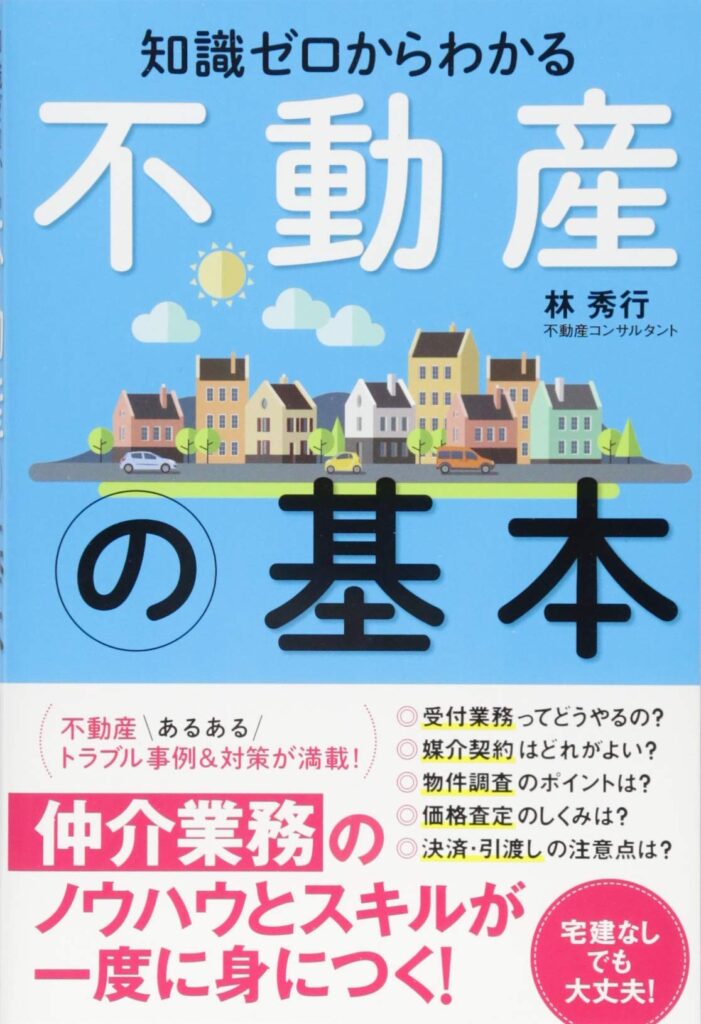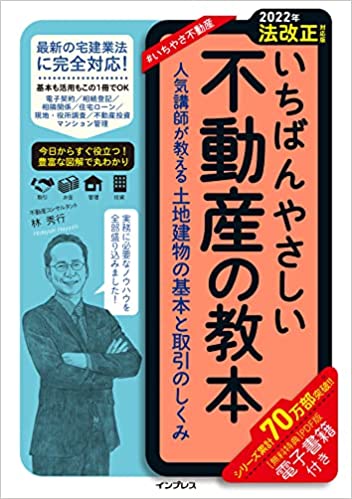【問 108】正誤問題
〔小問1〕
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、
原則として用途地域を定めないものとされている。
〔小問2〕
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
〔小問3〕
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、市町村長へ届出をしなければならない。
〔小問1〕解答:正
解説
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、
原則として用途地域を定めないものとされている。
〔小問2〕解答:正
解説
そのとおり。準住居地域の定義である。
〔小問3〕解答:誤
解説
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。届出ではない。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
解説動画は下の画像をクリック