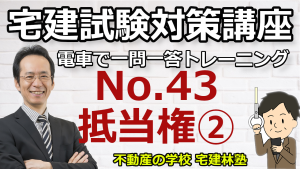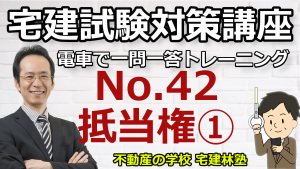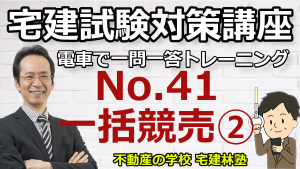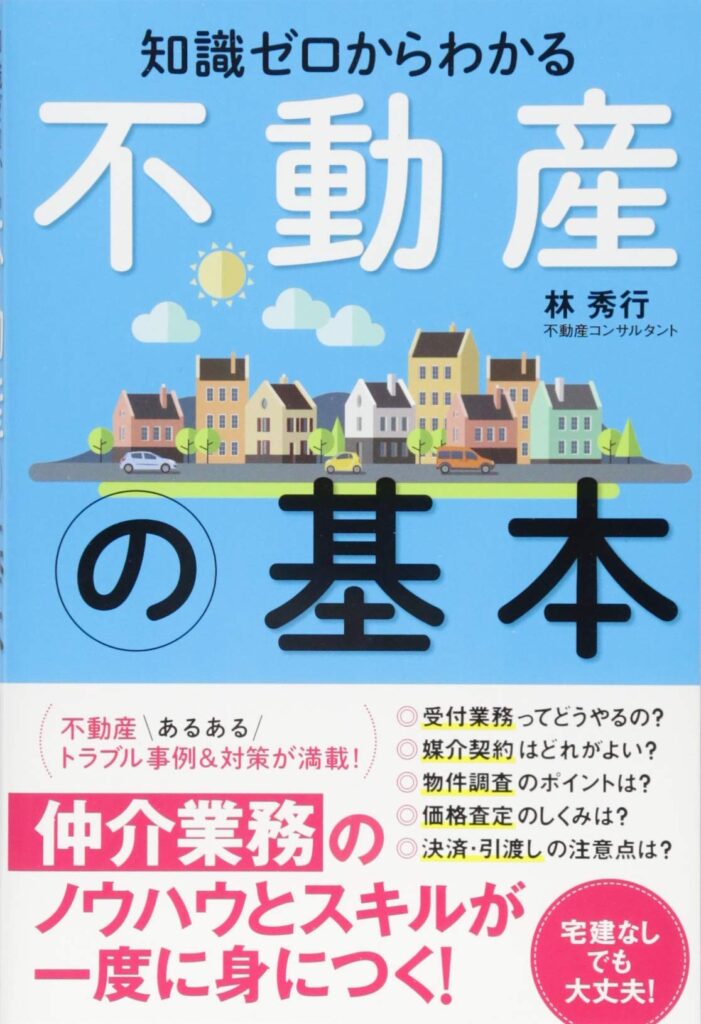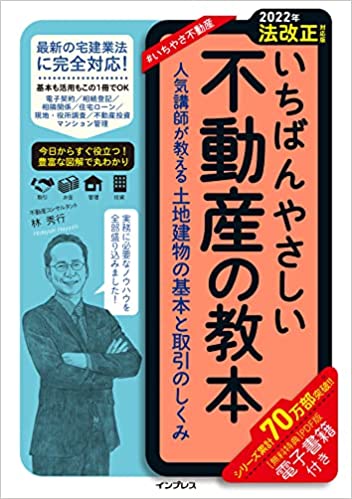【問43】正誤問題
〔小問1〕
Aは、Bを売主、Cを買主とするマンションの売買契約によって生じたCの売買代金債務について連帯保証人となった。BがAに対して履行の請求をしたときは、Aは、「まずCに催告せよ」とBに主張することができる。
〔小問2〕
BがAに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となっている。
CがAから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Aに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
〔小問1〕解答: 誤
解説:連帯保証でない保証債務の場合に、債権者が主たる債務者に請求せず直接保証人に請求してきた場合、保証人は、「まず主たる債務者に請求せよ」、と主張することができる(催告の抗弁権)。一方、連帯保証人には、催告の抗弁権はない。
〔小問2〕解答:誤
連帯保証人でない保証人が複数人いる場合、それぞれの保証人は等しい割合で義務を追う(分別の利益)。
一方、連帯保証人の場合、連帯保証人各自が債務の全額について保証債務を負担することになる。
したがって、Cは、Bから債務全額の請求を受けた場合、Dに半額を請求するよう求めることはできない。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
解説動画は下の画像をクリック