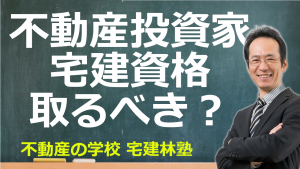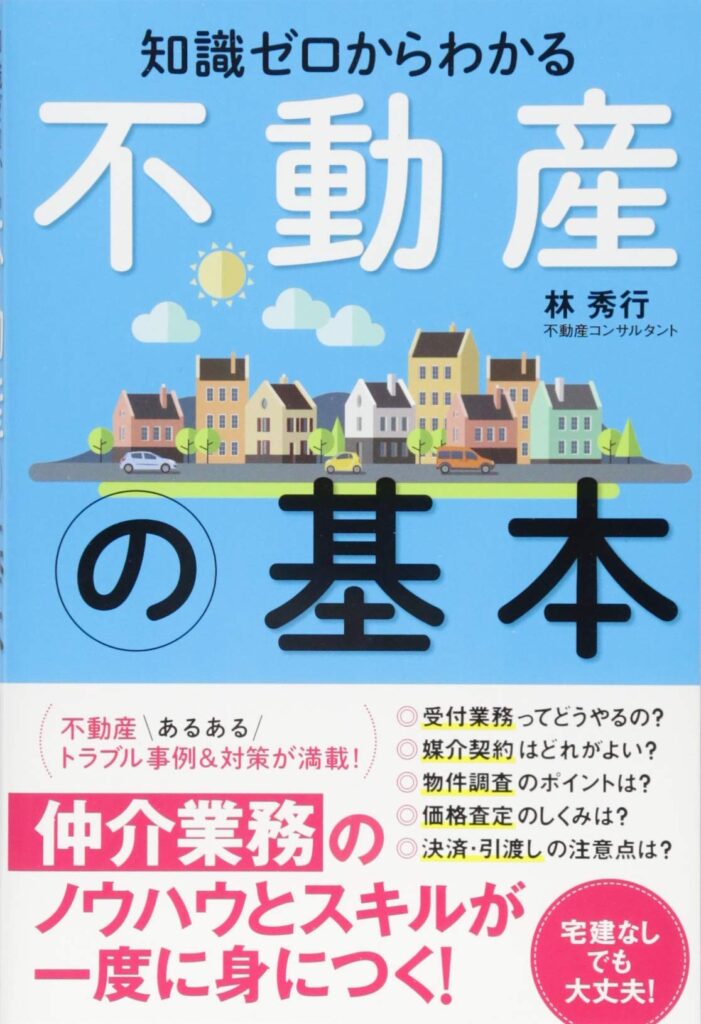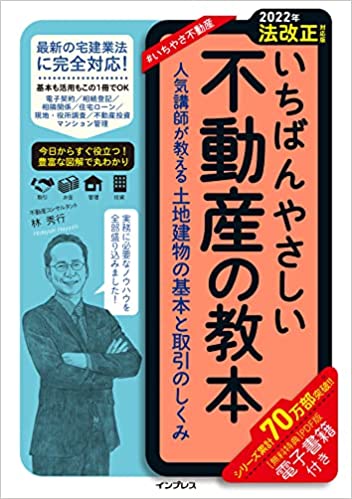今月10日に
「米銀シリコンバレー銀行が経営破綻」のニュースが流れたとき、
「いよいよ大きいのが来たか」と、身構えましたが、
リーマンショックのような世界同時株安の懸念はさほど大きくない
との見方が大方ですね。
ただ、日本の経済の足元は確実に悪化している気がします。
なんといっても物価の上昇が激しいです。
身近な例では、
建設業者の倒産が増加しています。
先月、
投資用ワンルームマンションなどの新築工事のUBM社が、破産しました。
経営悪化の原因は詳しいことは知りませんが、報道によると資材価格の高騰などの影響があるようです。
建築資材の価格が高騰すると利益率が下がり、赤字工事が増えることになるからでしょう。
小規模から中規模クラスの業者の場合、ちょっと信用不安が起こると急速にキャッシュフローが悪化するケースが多いです。
これからしばらくは特に建設業界は厳しい状況が続くでしょうね。